

広島で仏壇の修理修復の専門「音羽屋」の
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
七五三も法事も仏壇も同じ願い
なぜ七五三は
7才5才3才なのか?
なぜ法事は
三回忌や七回忌なのか?
この数字の意味は
たった一つの「〇える」
という願いからでした!
お仏壇には生きる
秘訣がいっぱい
職人が毎日
ブツブツ言ってます
(318日目)
↓ ↓ ↓

こんにちは!
広島で
お仏壇のことなら
音羽屋の山縣です
音羽屋では
まごころこめた
お仏壇の修復をとおして
「仏教のおしえ
で生きるヒントを」
「ご先祖の想いで
生きるチカラを」
イキイキした
ブツダンライフを
お届けしています!

こんにちは!
ラジオカーの林です

あれ!?
今日はなんでまた?

お隣で
取材だったので
新人とご挨拶です!

わざわざ
ありがとうございます!

はじめまして!
福山です
ここが「あの」
音羽屋さんですね

はじめまして!
・・・ん?
「あの」って
突撃となりの仏壇屋みたく
あいさつに来て下ったのは
RCCラジオカーの
リポーターのお二人さん
お隣の「おんづか」さん
という呉服屋さんへ
七五三を前に
子どものお着物について
聞きに来られたそうです

お着物のことなら何でもおまかせ!
七五三に限らず
お子さまのお着物
ご家族用のお着物
大切な節目のお着物
という方へ
お着物のことなら
「おんづか」さんへ相談
してみてくださいね

いつもおしゃれな平原さんと
ラジオの中でも
お話がありましたが
なぜ、七五三は
その年齢なのか
というのを調べてみると
・・・
昔は医療が
進んでいなかったので
子どもの死亡率が高く
7歳までのこどもを
「神さまの子」
として今よりも大切に
扱っていたようです
親として
子どもが無事に育つことは
大きな喜び
スクスクとした
成長を願っていく中で
それぞれの節目までの
成長を感謝して
お祝いをしたことが
七五三の由来だそうです
そして
3歳・5歳・7歳を
節目とした理由は
暦が中国から伝わった際に
奇数は「陽」で
縁起がいいということと
3歳で言葉を理解し
5歳で知恵がつき
7歳で乳歯が生え替わる
という
成長の節目の歳だから
だそうです
昔に限らず
今でもそうですが
節目とされる年齢を
「越えた」ときに
ここまで成長してくれた
というのを実感して
まわりへの感謝の気持ちが
わいてきますね
越えると言えば
法事の回忌法要の年数も
あることを
越えることが由来なんです
法事の意味は
以前書いたブログから
↓
なぜ、三回忌や七回忌と
「3」「7」という
節目に法事をするのか?
実は・・・
そもそもこの風習は
日本独自のもので
仏教の風習ではありません
日本独自で発展して
3と7になった理由は
「十三仏信仰」から
という説もありますが
それよりも
3と7は仏教では
大切にされている数字
ということからなんです
「7」は
迷いの姿である
「六道」の世界を超えて
悟りに至ることを
暗示していて
そこから「6」を超える
「7」という数字が
迷いを超える
という意味で
大切にされているんです
「3」も同じで
「2」を超える
という意味
「2」超えるとは
「有・無」
「勝・負」
「損・得」
というような両極端に
偏った考え方を離れた
中道の生き方を
意味しています
中道と言うのは
仏教でさとりを目指す上で
大切な考え方
お釈迦様も
ご自身の息子さんに

二を超える
生き方をせよ
と仰られました
これらのことから
毎年の法事は無理でも
せめて仏教で大切にする
3と7の年忌だけは
お勤めしようということ
が習慣化したそうです
つまり大切なことは
数字へのこだわりではなく
その数字に込められた
「迷いや偏りをこえる」
ということ
日々のお仏壇のお参り
だけではなく
法事を執り行うことで
仏教の教えにふれ
生きるヒントにして頂けると
嬉しいですね

音羽屋では
まごころこめて
お仏壇を修復することで
仏教の教えで
生きるヒントを
ご先祖さまからは
生きる力を
イキイキできる
ブツダンライフを
お届けします
本日もお読みいただき
ありがとうございました

ちなみに・・・
5歳を超えた娘は
大人女子のような
発言が増えてきて

ちゃんと運動会に
来てくれたから
お仕事遅くなっても
いいよ~
と時間外労働の
許可を頂きました

どうやら
すでに手のひらで
転がされているようです
な~む~
関連記事
カテゴリー
- おすすめ (6)
- お仏壇でやってはいけない事 (13)
- お仏壇とご先祖のこと (30)
- お仏壇のこと (201)
- お仏壇の火事に注意してください! (7)
- お仏壇をコンパクトにするには? (9)
- お仏間リフォームのポイント! (7)
- お供え物について (18)
- お参りによる効果とは? (45)
- お客さまのお声 (12)
- お寺の掲示板 (4)
- お神輿のこと (4)
- お香 (3)
- キレイにするポイント! (18)
- ご処分する時のポイント! (14)
- ご法話で聞いたこと (30)
- サタデーナイト仏教 (2)
- その他 (98)
- ダジャレ (3)
- フリースタイルな僧侶たち (1)
- プロフィール (4)
- 生い立ち (2)
- ラジオ (43)
- 事例 (224)
- 仏事のお話し (7)
- 仏具のちょっとした注意点! (9)
- 仏具の並べ方のポイント! (7)
- 南無レター (10)
- 女子高生、僧になる。 (6)
- 宗教について (3)
- 家系について! (5)
- 引き継ぐときポイント! (28)
- 日常の仏教 (137)
- 神仏の不思議な体験のおはなし (12)
- 神社やお寺 (29)
- 移動や引越しのポイント! (31)
- 空き家について (10)
- 終活について (3)
- 遺影写真について (1)
- 音羽屋ってこんなお店! (48)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
音羽屋インスタ
月別記事
- 2026年1月 (10)
- 2025年12月 (22)
- 2025年11月 (6)
- 2025年10月 (12)
- 2025年9月 (16)
- 2025年8月 (21)
- 2025年7月 (22)
- 2025年6月 (22)
- 2025年5月 (25)
- 2025年4月 (28)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (26)
- 2024年12月 (27)
- 2024年11月 (23)
- 2024年10月 (27)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (30)
- 2022年10月 (33)




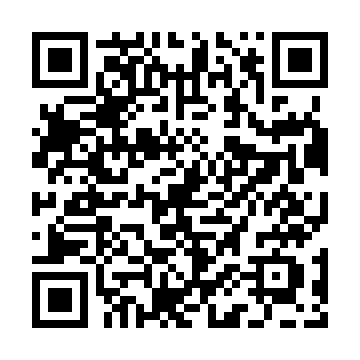




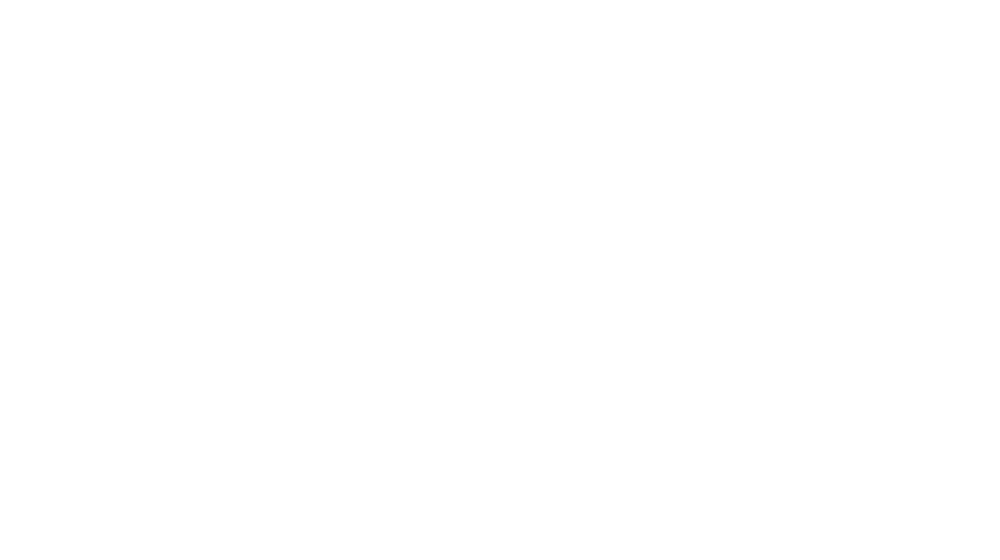
















Profile
お仏壇の修復業を主として、広島県内を中心に仏壇に関するお困り事を解決しています。
中国地方で唯一工法特許を取得した洗浄技術の使用許可を持っています。
お仏壇を美しく、よみがえらせることで、より多くの家の、その家らしさをよみがえらせていきます。
音羽屋では、まごころこめて、お仏壇を修復することで
プロフィール詳細「仏教の教えで生きるヒントを」
「ご先祖さまからは生きる力を」
イキイキできるブツダンライフを伝えていきます!